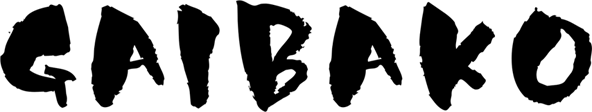廃墟の町
ーーーああ、いつだって、君はそこにいたのに。
僕はいつも、何の考えも無しに失ってばかりだ。
だから、僕はまた廃墟と共にいるのに。
鬱蒼と茂った森の奥。
道なき道をかき分けて二時間ほど歩くと、唐突に町が現れる。
ーーーいや、町だった場所と言った方が正確か。
ほんの五百年ほど前までこの場所は「町」だった。
今となっては見る影もない。
本当に町だったのかどうかすら、今となっては嘘だったのではとも思えてくる。
噴水の跡を眺め、複雑にからみついた蔦をなんとなしに引っ張りながら、今にも壊れそうなベンチに腰掛ける。
腰掛けた瞬間、ギシ、と嫌な音を出したが、五百年前と同様に僕の体重を支えてくれた。
ベンチとしての役割はまだ忘れていないようだ。
大きく深呼吸する。
このあたりはまだ空気が綺麗な方だ。
森の外は冗談でもいい空気なんて言えない。
この森もいつまで無事でいられるものやら。
まあもってーーーあと千年くらいか。
ああ本当に嫌になる。
時間が流れるのが遅い。
不死になんてなるものじゃないなと、八千年ばかり生きてようやく思う。
死に方がわからないなんて、とんだ欠陥品。
不老不死にあこがれて、なってみたはいいものの、このどうしようもない虚無感は如何ともしがたい。
世界のどこかにはもう一人くらいいるのだろうか。
もしいないのであれば、僕は一生一人きりなのだろうか。
いや、死なないのだから「一生」という表現はおかしい気もする。
そんなくだらないことでクスリと一人笑う。
こんなくだらないことすら、言ってくれる人間はもういないのだ。
もしかしたら、世界のどこかには。
そんな期待をしつつ、いたとしてもまともな人間じゃあるまい、と達観する。
本当に、不死になんてなるものじゃないな。
五百年ぶりに人を載せたベンチに別れを告げ、町の中心へと足を進める。
もともとは石造りの家が立ち並び、果物を押し付けてくる商売人や昼間っから飲んだくれてる酔っ払いがいたものだが、当然今となっては人っ子一人いない。
かろうじて、『そこに何かあった』形跡が見て取れるのみだ。
風化が激しく、さらに問答無用で植物がすべての建造物を飲み込み、破壊しつくしてしまった。
森に比べたら開けているし高い木が生えているわけでもないが、単純にひどく寂しい気持ちになる。
植物の茎を折りながら、石畳の上をゆっくりと踏みしめて歩く。
風はなく、キン、と耳の奥に響いてくるほどの静寂。
その静けさを自分の足が奏でる足音が破壊していく。
しばらく歩くと、ある場所だけ綺麗に整えられた空間が見えてくる。
蔦もなく、他の場所とは比べ物にならないほどに清掃されたその場所。
僕は、ただいま、と一言つぶやく。
一年前に言ったように。
二年前に言ったように。
五百年前に言ったように。
ざざ、と少しだけ風が吹き、木がざわめく。
一年ぶりの訪問を歓迎してくれているのか。
それとも、一年も放っていくなんて、と罵倒されているのだろうか。
僕が愛したあの人が眠る場所で。
時間は、残酷だ。
僕にとってこんなにもゆっくりなのに、
周りはあっという間に変わっていってしまう。
ほんの、ほんの少しの間のつもりだったのに。
僕も同じ時間の流れを生きてきたはずなのに。
まるで、一度見た町が、次に見る時には廃墟になってしまうのが当然だとも思えてくる。
今までいくつの町を訪れただろう。
いくつの町が廃墟になっただろう。
何人の人を愛しただろう。
何人の墓を建てただろう。
いつまでもいつまでもこの後悔は続く。
町は朽ちても愛は朽ちず。
そんな洒落た言葉も、今となっては古めかしい。
ざざ、とまた木々がざわめく。
もう帰れ、ということなのだろうか。
僕に帰る場所など無いというのに、残酷な彼女だ。
僕は次の町に行くことにする。
廃墟になってしまった次の町へ。
未だ朽ちていない、愛を辿るために。
『不死者ザメルの独白』